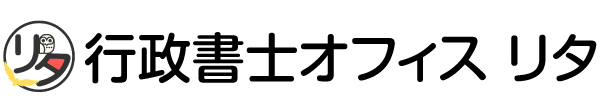1. 猫を失った飼い主の姿から考える、災害と動物の問題
岩手県大船渡市で発生した山火事の報道をご覧になった方も多いことでしょう。私もそのニュース映像を見て、焼け焦げた住宅の中から飼い猫が逃げ出せずに命を落としたこと、そしてその事実に呆然としながら立ち尽くす飼い主の姿を目にしました。ペットも家族である、という思いを強く持つ私にとって、非常に胸が痛む出来事でした。このような現実を目の当たりにして、災害が起きたときに猫と飼い主がどうやって命を守れるのか、行政書士としての役割を見直す契機となりました。
2. 猫の避難が抱える独特の難しさ
猫は非常に繊細な動物で、災害時の避難においては犬以上に困難が伴います。例えば、住環境の変化に対する適応が遅く、引っ越しや模様替えといった小さな変化でも強いストレスを受けてしまいます。慣れない場所に移されると食事を拒否したり、排泄を我慢したりすることがあり、長時間それが続くと健康に深刻な悪影響を及ぼします。特に災害時の避難所では、音・匂い・人の多さなどから極度の緊張状態に陥ることもあります。したがって、猫の避難には、普段使用しているケージ、寝床、トイレ、フードや水入れをそのまま持参し、自宅の延長のような安心できる環境を一時的にでも再現する必要があるのです。
3. 避難所の環境と飼い主が直面する現実的な課題
さらに、避難所には猫アレルギーを持つ人がいる場合もあり、動物の受け入れが制限されるケースもあります。鳴き声や排泄臭、抜け毛への苦情が発生することもあるため、飼い主としては周囲への配慮も不可欠です。また、猫はキャリーケースに慣れていないと、中で暴れたり、逃げ出したりするリスクがあり、避難中の安全確保にも影響します。そのため、平常時からキャリーケースや「猫を安全に閉じ込めて運ぶための移動用の箱(移動用ケージ)」への慣れを促すトレーニングや、ハーネス装着の習慣化、緊急時の避難ルート確認、猫用の備品をまとめた避難袋の常備など、事前の備えが極めて重要です。
4. 行政書士にできること〜法的支援と文書整備の力〜
このような状況に対して、獣医師や保護団体は現場での医療・保護・飼育支援を中心に活躍しますが、行政書士は「制度」と「書面整備」のプロフェッショナルとして、異なる角度からサポートが可能です。
たとえば、ペットを連れて避難所に入ることが難しい状況では、やむを得ず車中泊をしたり、損傷の激しい自宅に猫とともにとどまったりする選択をする飼い主が出てくることが想定されます。雨漏りや電気・水道の停止といった劣悪な環境でも、猫を置いて避難できないという強い思いから、危険を承知で自宅に留まるケースが想定されるのです。
このようなリスクを未然に防ぐには、避難所のペット受け入れルールをあらかじめ整備し、飼い主・行政・避難所運営者の三者で合意を形成しておくことが大切です。行政書士は、そうした協定書や利用規約を、わかりやすく、実情に即して作成することができます。
また、災害後には、住まいの損壊に関する罹災証明の取得、保険金請求、動物病院での治療費請求、さらには迷子になったペットの所有権確認といった、さまざまな行政手続きが発生します。特に高齢の飼い主や初めて手続きを経験する方にとっては、何から始めればよいかわからないという不安がつきまといます。行政書士は、そうした方々のそばに立ち、手続きを一つひとつ丁寧にサポートする「身近な法務アドバイザー」として、心強い存在でありたいと考えています。
5. 防災計画に行政書士の専門性を活かす
また、行政書士は地域防災計画や避難所運営マニュアルの策定に関与することも可能です。地域の自主防災組織や自治体との協働を通じて、ペット同伴避難に関する章を加えること、ペット管理責任者の配置、避難所内で人とペットができるだけ快適に過ごせるようにエリアを区切る取り決め(エリア分けのルール)の整備、さらには飼い主向けの簡易マニュアルやチェックリストの作成といった、制度面からの支援も行うことができます。書類作成や合意形成を得意とする行政書士だからこそ、災害時の混乱を最小限に抑える備えに貢献できるのです。
6. 飼い主に求められる備えと連携の姿勢
猫と暮らすご家庭が、災害に備えて具体的に何を準備すべきか。その答えは「平時からの準備」と「専門家との連携」にあります。猫用の備品を取りそろえるだけでなく、地域の防災訓練に参加したり、行政書士や獣医師などの専門家に相談しておくことが、いざという時に必ず役立ちます。
7. 日常から始める備えの大切さ
こうした災害への備えは、何よりも「平時からの行動」が鍵になります。災害が起きたとき、慌てずに猫と一緒に避難できるよう、日頃からの準備を少しずつ始めてみませんか。その一歩が、大切な命を守る力になるはずです。当事務所でも、その備えのお手伝いができればと考えております。