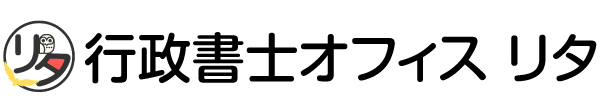- 問題提起
「自筆証書遺言」というと、全て手書きで書かなくてはならないのでしょうか?
財産の全部を手書きで書くと財産が多いため、ものすごく手間がかかります。また、多くの文章を手書きするため、誤字脱字の危険性も高くなります。
遺言書の全てを手書きすることを考えると自筆で遺言書を書くことを躊躇するのではないでしょうか?
そこで今月のコラムでは、「自筆証書遺言」について書きました。 - 遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類があります。一般には、公証人が作成する「公正証書遺言」と遺言者自身が作成する「自筆証書遺言」が利用されます。
今月のコラムでは、後者の「自筆証書遺言」について記載します。 - 自筆証書遺言について
- 民法第968条第1項の要件
民法第968条第1項では、自筆証書によって遺言をするには、遺言書の全文、遺言書の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印する必要がある旨記載されています。 - 財産目録
しかし、財産目録については、自書によらないで、遺言書に別紙で添付することができます(民法第968条第2項)。
例えば、不動産の場合は、不動産(土地・建物)の登記事項証明書の原本もしくはコピーを添付する方法で作成することができます。
また、預貯金等については、銀行の通帳やカードのコピーを財産目録として作成することができます。その際には、銀行名、支店名、口座名義、口座番号が明確に読み取れるように、鮮明に写っていることが必要です。
さらに、財産目録をパソコンで入力して作成することもできます。その際の注意点として、不動産は登記事項証明書の記載、預貯金は銀行の通帳の記載、その他財産を特定する資料の記載どおりに財産目録に入力してください。 - 共通する注意点
別添の財産目録(不動産登記事項証明書・通帳・パソコンで作成した財産目録全てに共通)の各ページに署名し、押印する必要があります。この署名は必ず、自書する必要があります(民法第968条第2項)。
また、訂正の際には、別添の財産目録も遺言書本文と同様の方法になります(民法第968条第3項)。つまり、①変更場所の指示、②変更した旨、③署名、④変更箇所への押印、です。しかし、㋐訂正すると財産目録は第三者に読みづらくなること、㋑訂正箇所の部分を新しく作成することが容易であること、㋒むしろ訂正した場合手間がかかる、といった理由から訂正がある場合は、財産目録の訂正箇所のページを新しく作成することをお勧めします。 - まとめ
以上のように注意事項がいくつかありますが、自筆証書遺言書は必ずしも全文を自書する必要がありません。
本コラムでは、自筆証書遺言の自書を必要としない部分について記載しました。しかし、自筆証書遺言には他にも記載について注意することがあります。また、法務局で遺言書を保管してもらう制度「自筆証書遺言書保管制度」を利用する際にも、別途注意事項があります。本コラムで記載していない自筆証書遺言の注意事項については、また、別の機会で記載したいと思います。
- 民法第968条第1項の要件
※個別事項につきましては、当事務所にお問合せいただくか、毎月一回開催する無料相談をご利用ください。無料相談の開催日時は、当事務所ブログに記載されます。当事務所ホームページのトップページ下部の関連リンクから当事務所ブログをご覧いただけます。