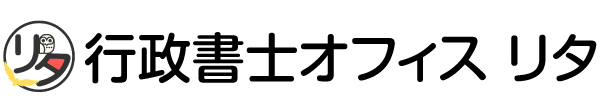今年の年末年始は、長くて9日間あるそうです。
帰省される方も、また、それを迎える方も多いことと思います。
親戚一同が集まる機会に遺言書を書こうと思われている方は、お子様方と話し合われてはいかがでしょうか?
今月のコラムはそんなお話です。
- 子供の立場
自分の親がどれだけの財産を所有しているか把握していない子供は多いと思います。この私自身、自分の親がどれだけの財産を所有しているか把握していません。しかし、私の場合、幸いにも、両親は多くの不動産を所有していません。また、両親との距離も近いため不測の事態に対処することもできます。
しかし、両親の遠方に住居を構えている方や両親が不動産を多く所有している方は、相続等において負担が大きいと思います。
高齢の両親の生活や介護については、私の専門外ですので、ここでは、相続する財産に限ってお話します。 - 不動産の相続
相続した財産が、不動産の場合、その不動産を維持・管理する必要があります。これは、家屋などの建物だけでなく土地についても同様です。
不動産を所有すると、固定資産税がかかります。これは、誰でも想像できることですが、固定資産税以外にも、建物の場合、水道・電気などのライフラインの基本料金、火災保険などの保険金、台風などの災害に被災するとそのままにしておくことはできないので修繕費が必要になります。
土地の場合も、固定資産税の他に、土地を維持するために草刈りをする必要があるので、業者に依頼するとその費用がかかります。
不動産の場合、金銭だけでなく、その維持管理のために定期的に現地に赴き、掃除や草刈りなどをする必要があります。
相続する子供たちが遠方に居住していると、その労力は大変なものになります。だからこそ、相続する子供としてみれば、不動産ではなく、預貯金などの金融資産を多く相続したいと考えている人が多いと思います。 - 誰に何を相続させるのか。
遺言書を作ろうと考えている方は、誰に何を相続させるのか悩まれると思います。- 私の場合なら、自分の配偶者に全てを相続させます。なぜなら、子供たちにも家庭があり、自分の子供つまり孫たちのことで手一杯で、自分の親まで手が回らないと思うからです。
配偶者に財産が有れば、子供の手を煩わせることなく、介護施設等を利用することができます。また、私は税金の専門家ではないのですが、現状、配偶者の相続については優遇処置が大きいと思われるからです。
さらに、配偶者が必要な費用を相続財産から消費することで、子供たちが相続する財産が減り、その分子供たちが相続する時の相続税の負担も軽くなると思うからです。 - しかし、子供たちが相続する場合は、より問題が難しくなります。なぜなら、前述のように不動産については、負担が大きい場合があるからです。市街地で誰がみてもすぐに売れる土地ならばよいのですが、農地や山林、過疎地の実家などを相続すれば、負担だけが重くのしかかるように思われます。ましてや子供の住居が遠方にある場合は猶更です。
- 私の場合なら、自分の配偶者に全てを相続させます。なぜなら、子供たちにも家庭があり、自分の子供つまり孫たちのことで手一杯で、自分の親まで手が回らないと思うからです。
- この機会に
親戚一同が集まる年末年始のこの機会に、皆さんで相続について話し合ってはいかがでしょうか?
遺言書の作成を考えられえている方は、もらう側の意見を聞くいい機会です。また、子供たちも自分の親がどのような財産を所有しているのか、不動産など現状どのくらいの負担をしているのか、色々なことを聞くいい機会だと思います。